春は芝生の成長が本格化する大切な時期。このタイミングで**「目土入れ」**をすることで、芝生の健康を保ち、ふかふかの緑のじゅうたんを作ることができます。しかし、「どんな目土を使えばいいの?」「どうやって入れるの?」と疑問に思う方も多いはず。
この記事では、春の芝生の目土入れの重要性や具体的な手順、おすすめの目砂や道具を詳しく解説します!
なぜ春に目土入れが必要なのか?
春の目土入れには、以下のようなメリットがあります。
✅ 芝生の生育を促進する(根がしっかりと張る)
✅ 凹凸を均すことで芝刈りがスムーズに
✅ 芝の根元に栄養を補給し、健康な成長を促す
✅ 乾燥や病気から芝生を守る
✅ 芝生の密度を高め、雑草の侵入を防ぐ
特に冬を越した芝生は、部分的に芝が薄くなっていたり、地面がデコボコしていたりすることが多いです。春に目土を入れることで、芝生のコンディションを整え、新芽が健康に育つ環境を作ることができます。
芝生に適した目土(目砂)の種類とは?
目土には**「芝生の根を強くする」**という目的があるため、適切なものを選ぶことが大切です。
おすすめの目土・目砂の種類
| 目土の種類 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| 山砂 | 水はけがよく、芝の発根を助ける | 目土として最適、排水性向上 |
| 川砂 | 粒子が細かく、均一に仕上がる | 目土が均一になりやすく、手入れしやすい |
| 黒土入りの目土 | 有機質が多く、栄養を補給できる | 土壌改良も兼ねたい場合におすすめ |
| バーク堆肥入りの目土 | 微生物が豊富で芝生の健康を維持 | 有機質を補給し、長期的な育成向け |
おすすめは 「山砂」+「川砂」のブレンド です。排水性と芝の根の成長を促す効果があり、バランスの取れた目土になります。
バロネスなどの砂はいいと思うんですが、庭のサイズによってはとんでもない金額になってしまうのでご注意を。
目土入れに必要な道具
適切な道具を使うことで、均一に目土を入れられ、作業が効率的になります。
目土入れの必須アイテム
- ふるい(目土を均一に撒く)
- レーキ or トンボ(目土を均等に広げる)
- スコップ(目土を取り扱いやすくする)
- ジョウロ or 散水ホース(目土後の水やり)
- サッチングマシーン(オプション)(目土前の枯れ芝除去)
特に、「ふるい」を使うと細かい砂を均等に撒くことができるので、芝生がムラなく成長しやすくなります。
春の芝生の目土入れ手順
1️⃣ 芝生の掃除とサッチング
まず、枯れ芝や落ち葉を取り除きます。サッチングマシーンやレーキを使って芝の根元の通気を良くするのがポイント。
2️⃣ 芝生の凹凸をチェック
芝生の表面にデコボコがないか確認。特に凹みがある場所には重点的に目土を入れる準備をします。
3️⃣ 適量の目土を撒く
スコップやふるいを使いながら、芝生全体に薄く均等に目土を撒きます。厚さ1~2mm程度が理想。
4️⃣ レーキやトンボで均等にならす
目土が芝の隙間にしっかり入るように、レーキを使って均等にならします。ここで厚くなりすぎると、新芽の成長を妨げるので注意。
5️⃣ たっぷりと水やりをする
最後に散水ホースやジョウロを使って、しっかりと水やりをします。目土がしっかり芝生に馴染み、根元に届くようにするのがポイント。
目土入れの際の注意点
✅ 一度に厚く入れすぎない(根が窒息してしまう)
✅ 風が強い日は作業を避ける(砂が飛び散りやすい)
✅ 雨の翌日は避ける(土が湿っていて均等にならない)
✅ 春~初夏(3月~5月)が最適(新芽が成長するタイミング)
✅ 目土はこまめに薄く入れるのがコツ
特に、「目土を厚くしすぎると芝が光合成できずに弱ってしまう」ため、1~2mm程度の薄い層にするのがポイントです!
まとめ
春の目土入れは、芝生の成長を促進し、健康な芝生を維持するための重要なメンテナンス作業です。適切な目土を選び、道具を活用しながら丁寧に作業を行うことで、美しい芝生を育てることができます。
✅ 春の目土入れのチェックリスト
✔️ 山砂+川砂のブレンドが最適
✔️ ふるい・レーキ・スコップを活用
✔️ 1~2mmの薄い層に均等に撒く
✔️ 水やりをしっかり行う
✔️ 風や雨の日を避ける
この春、しっかりと目土入れをして、ふかふかの美しい芝生を育てましょう!


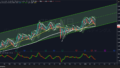
コメント